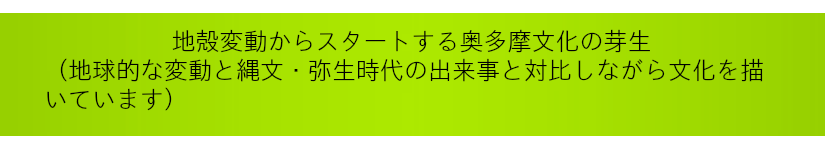![]()
2014.8.30

奥多摩の縄文時代
新代生は第三記と第四記に分けられていて、第四期は人類が誕生した時代とされている。もともと人類出現以降の時代を第四紀とよんでいたが、いつだったかはまだ解っていない。それで約160万年前から現在も含めて第四記と呼んでいる。第四紀の地球環境は氷河期と間氷河期を繰り返しているといわれ、現代はあたたかい間氷期にあたる。
日本に人間が渡って来て、住み着いたのが70~80万年前という説があり。歩けるようになるまで、具体的にどのように進化して、どれぐらいの果てしない年月が掛かったかは永遠に解らないかもしれない。しかし、海に山に哺乳類が生息し、人間は集落を作りながら生活を営んできたことは事実である。
今から20~70万年ほどまえ、小御岳火山という単独の噴火山が活発に活動していたとされている。この山は数多くの噴火によって溶岩や火山灰が積もってできた2500メートル程の高さだったと考えられています。
この小御岳火山が活発なころ、武蔵野のまだ海の中にあった部分が徐々に隆起し、現在の武蔵野の原型が次第に姿を表してきます。子御岳火山の火口壁の一部は、富士山の五合目の泉ケ滝で見ることができるという。
さらに2~7万年ほど前になると、古富士火山が小御岳火山の南側で始まったとされている。このころの人類は縄文人と呼ばれていて、縄文時代の集落あとは縄文土器と一緒に各地で発見されている。武蔵野の山沿いで、縄文人が工夫を凝らしながら普通に生活していた、ウルム氷河期にあたる2万5千年ほどまえ、古富士火山の活動期の中でも大規模な噴火があったとされる。
恐れおののき、もう、この世の終わりだと思わせた人類としての自然の脅威を認識させられた出来事であった。その噴火は、関東地方にもふりそそぎ、今の東京の上空を暗闇にし、火山灰は武蔵野に数メートルの高さに積もったとされている。現在その降り積もった層のことを関東ローム層と呼んでいる。古富士山は噴火を繰り返す度に大きくなり、約2700メートル程になっていたといわれている。
現在の富士山は、小御岳火山と古富士火山の間で噴火口として活動を始めたという。この噴火口の新富士火山の噴火は、小御岳と古富士を埋め尽くした。1万年前頃から噴火の規模が徐々に小さくなり、8千年前頃に現在の美しい姿とほとんどかわらない富士山を形成したという。
記録がはっきりしている部分では、平安時代から江戸時代まで20回ほどの噴火記録が残っている。最後の噴火と言われた1707年の宝永4年の噴火は、江戸の大空を覆い、昼間でも明かりを灯さないと本が読めなかったという記録が残っている。
昭和23年国分寺の関東ローム層の中から、初期の石器が見つかった。それまでは、関東ローム層の中に石器はないというのが定説となっていた。それは何十万年も前に、富士火山ができる前の小御岳火山の大噴火に恐れおののきながら、武蔵野で人類が生活を営んでいた証拠みたいなものになり、関東ローム層の中に石器はないという定説は覆されたのである。
人類学者は、日本列島に渡ってきた人間の身長は150センチほどであったと推測している。ギリシャ彫刻の目のほりが深くてゴリラに似たような顔の形だ。彼らは最初、木の実のほかに死んだ動物の肉を食っていたと思われる。それはまだ、石で木の実を割るとか石を投げるとか、道具というより猿知恵とほとんど変わらなかった。そのうち石を投げたり、大きな石を上から落としたりして動物を捕り始めたと思われている。
15万年ほど前に、30センチぐらいの握りヅチが使われるようになり、イノシシやシカなどの動物を追いまわすようになる。それは命を張った捕獲作業で、捕獲率は悪く、苦労の割りに合わない恐怖の捕獲作戦だったと思われる。石器の使い分け、道具の改良は生命の安全を図るために10万年以上にも渡っている。硬い石の使い分け、石の削り方、矢じりなどの工夫を基に弓やヤリなどが使用されるようになるのは1万数千年前だと推測されている。まだまだ、人類が地球を支配するようになるまではほど遠い状態だった。
狩をする際に自分たちの保身を図れる道具の改良はいつになっても大事なテーマである。道具を考え、狩をする、動物たちは身が軽く逃げ足が速い、また考える。そうして考えれて使用されていた。石器はヤリ、ナイフのような物や穴をあけるキリのような物であった。武蔵野で発見されている。石器の量は割合多く、1万年から7千年前に使われていたものだと推測されている。関東ローム層の中にはもっと古い石器が寝ていると考えられている。さまざまな道具を考案し、徐々に逃げ足の速い動物に対しても効率がよくなっていく頃、東京は大半が陸地になっていたと思われる。
陸地が広がっても、まだまだ生活を営める環境でなかったと思われる。JR青梅線の終点、奥多摩駅からバスで16分ほどのところに奥多摩湖(小河内ダム)がある。そこから登山道徒歩3時間ほどの御前山(1405m)の標高1000mの地点から1万年前と推定される黒曜石の矢じりを考古学者が発見している。
信州長野の黒曜石が奥多摩の御前山標高1000mの地点から発見されたのである。この黒曜石は、長野の霧が峰などから噴出した溶岩石のガラス質が固まった物だと推測されている。それは、奥多摩から尾根沿いに他の原人との物々交換がすでに行われていた事を示して、当然、日本の他の地域に原人が渡っていたということである。
長野県の霧カ峰(標高1700m)付近の黒曜石を調べているうちに、偶然、長野県和田峠(標高1500m)の神代杉の写真を見つけた。
(http://www.asahi-net.or.jp/~kc5a-kjmt/kigi/jindaiky.htm)
また、長野県生島足島神社の境内には樹齢1000年ほどの神代ケヤキがある。奥多摩の手前、青梅市御岳の御岳神社(標高929m)には国指定天然記念物の神代ケヤキがある。日本の宗教の始まりは山岳宗教であるということを読んだ気がする、古代から人類が住んでいたところは山岳であり、縄文人が長野県に行く時なども特徴のある巨木があり、それを道しるべとしていたのかもしれない。
それにしても、奥多摩の御前山から尾根づたいにどうやって長野県山々まで行けたのだろうか。狩をし道を迷い、偶然にたどり着いたのだろか。最初は偶然でも、それから文化の交流が始まっているのは間違いない。地図もなくコンパスもなく、太陽の位置や月の位置を頼りにしたのだろうか。奥多摩から出るはずもない黒曜石が見つかったということは、方向を見極める方法を持っていたと言う事であし、道しるべを決めていたということである。たいへんなことであったと思う、体力もいるし、恐怖感にも勝たなければならないし、帰ってこれるという保障はない。
顔と身体つきは原人の血を受け継いでいる現代人の私は 、青梅から新潟に行った際、奥多摩の尾根づたいでなく、青梅線の河辺駅から青梅特快と新幹線を使って。しかも、尾根づたいでなく電車なのに、トレッキングシューズをはいて、武蔵野原人は尾根づたいを裸足だったろうに。
私が新幹線の中でトレッキングシューズを履いて本を読んでいると、車内販売のお姉さんが、コーヒーはいかがですか、ビールはいかがですか、お土産はいかがですか。と、廻って来るもんだから、コーヒーを飲もうかと思ったが、喉がビールを欲しがり、あとは新潟まで寝てしまった。
私が新潟に向かったのは、あとから長野の霧ケ岳まで行って黒曜石を手に入れるためではなく、新潟の仲間5人と料亭で食事と酒を飲む為に、遅くまで飲んで一泊して、新潟から尾根づたいでなく、トレッキングシューズを履いて、やはり新幹線で帰ってきた。お酒の交流のためであって、文化の交流のためでなはなかった。
私が武蔵野原人で、黒曜石を手に入れてこいと言われたら、腹が痛いとか頭がクラクラするとか言って、なんとか先延ばしに避ける方向を選ぶだろう。文化の発展は理屈や言い訳をしていたのでは、恵まれた環境は訪れてこないのかもしれない。
尾根づたいの文化の交流により、武蔵野原人は、ガラス質のナイフにでも、矢じりにもなる貴重な黒曜石を手に入れた。肉を切ったり皮はぎをしたり、皮の脂肪分を削ぎ落としたりして衣類となる毛皮を作った、矢じりの先は黒曜石のキラリとした物に変わり、動物の殺傷能力も向上した。
尾根づたいの文化の交流により、武蔵野原人は、ガラス質のナイフにでも、矢じりにもなる貴重な黒曜石を手に入れた。肉を切ったり皮はぎをしたり、皮の脂肪分を削ぎ落としたりして衣類となる毛皮を作った、矢じりの先は黒曜石のキラリとした物に変わり、動物の殺傷能力も向上した。
この頃になると、火は最初動物から身を守るために使われていたのが、肉を料理するのに使われていたという。肉の料理の仕方は、火で肉をあぶるだけでなく、焚き火の中に石を投げ入れ、熱を持った石を並べその焼き石の上に肉を置き、熱が逃げないように肉の上に料理に差し支えのない草を掛け、さらに砂を掛けるという蒸し焼きをしていた可能性があるという。その根拠は、昭和35年ごろに国分寺市本町で石器などと一緒に数個の焼き石が発見されたことによる。
最初は生のままで食べていたのが、生臭さを消し食べやすくするためにいろいろ工夫していたと思われる。そうでないと焼き石の方法までたどり着かないだろう。火を焚いていて、たまたま無意識に横に置いていた肉が余熱で表面が硬くなったのを見て、火の中に投げ入れてみたり、火のそばに置いてまんべんなく廻したのか定かではないが、最初はそうであったと思う。それがそのうち焼いた石を使って肉を料理したとするなら、やはり人類は単なる哺乳類でなく、考える葦であったということになる。
奥多摩以外の集落との交流により手に入れた黒曜石を、いろんな形の道具に加工し収獲率の上がった武蔵野原人は、ドングリやクルミなどの木の実とイノシシやシカなどのほかに川魚も加わり、さらに保存食目的の干物も食料として考え出されている。それに伴い集落の周囲にある森の中から木のツルを利用しカゴを編み上げ、収納目的の生活必需品の発展へと結びついてゆく。
食料としての肉と魚それと木の実、それを火を利用して料理する。さらに干物にして保存食の利用、それを入れるカゴ、皮をなめした衣類、やがて武蔵野原人は、今まで慣れ親しんできた地を離れて多少移動しても差し支えなくなる。それは山を降り、新しい環境を求めての移動へとつながってゆく。
新たな環境を求めての移動は、定住地を求めてのものなのか、食料の木の実や動物や川魚などが豊富な場所を求めての移動なのか知るよしもないが、住居あとの遺跡などを基に推測すると、何人かが寝泊り出るほどの浅広の穴を掘りそこを木の枝や萱などを利用して覆うような住居で、簡単にバラバラになるものだった言われている。それは定住地を求める移動でなく、家族での生活を優先的に考慮した形式のいつでも簡単に解体でき、また簡単に作れる住居だった、その移動はやがて数家族での移動につながっている。現に檜原や秋川で、隣り合ったいくつかの住居あとの遺跡と石器が発掘されているという。
数家族での移動は、ある程度の集団での定住地の開拓につながってゆく。集団での定住地暮らしは、より便利な狩猟道具の弓や土器作りが盛んに作り出されたといわれている、縄文時代へと入ってゆく。
縄文時代の生活用具の偉大な発明は粘土を利用した縄文土器と弓だといわれている。数家族での生活は最初木のツルやなどを利用してカゴを編み、食肉や川魚と木の実を入れて一定期間保存するために使われていた。しかし、カゴでは川で汲んだ水を一定期間置いておくことはできなかった。ザルと一緒だからである。最初の縄文土器は、今まで使っていたカゴの内側に偶然、粘土を貼り付けてみた。そしてそれで水を汲んでみたら水がこぼれなかったのである。のちにそれは、粘土を貼ってしばらく乾燥させ、乾燥したら火の中に投げ入れた。外側のツルでできていたカゴの部分たは焼けて無くなり、土器だけが残るという、木のツルと粘土と火のコンビネーションでさまざまな型となった土器へと繋がって行った物と推測されている。
弓は、殺傷能力は上がったが思ったとおり命中せず不安定だった。茂みの中や木の上に昇りそこから狙ったり、さまざまな工夫がなされ、当然命中率は高確率となった。しかし、次第に動物捕獲の為にだけでなく、殺傷能力と命中率の向上した便利な武器は人間同士の争いにも使われていたと縄文人の骨は物語っているといわれている。発掘された縄文人の骨には腕の骨や腰の骨に矢じりが深く突き刺さっていて、それのほとんどが斜め後ろから狙わないと刺さらない位置だという。武器の開発はさまざまな悲劇の始まりをも狩人に印象付け、それは動物だけでなく同じ人間同士の戦いの道具に確実に用いられていたのである。
奥多摩の氷川駅から徒歩30分程の所に、海沢という所がある。ここの下野原という所から石器と縄文土器が発掘されている。
矢じりとナイフ代わりに使われていた石器で、奥多摩産のチャート石と長野県和田峠・神奈川県箱根畑宿・神津島産の黒曜石のものであるという。チャートは梅沢や多摩川支流に沿った町内のいたる所に岩面が露出していて、奥多摩産のチャートは南関東一帯の遺跡から見つかっている。
梅沢下野原で見つかった石器は、石刃石(皮や肉をはぐための道具)・石錐(穴あけ用キリ)・石鏃(石製の矢じり)・石錘(魚網用のおもり)・ハンマー・すり石・石皿(木の実をすりつぶすための道具)。縄文土器は、深鉢・円筒小深鉢・円筒深鉢・釣手土器・隆起把手深鉢・浅鉢・蛇蛙把手深鉢(上部)で、また、白丸・西の平からは人面付深鉢(上部)土器が発掘されている。どちらも奥多摩湖の水と緑のふれあいの館に展示されている。
人間は自然体系が豊富でなければ文明は継続できない。縄文時代の始めの食料は木の実が主食である。その後、動物や川魚の狩猟で動物性タンパク質を取れるようになる。縄文人にしろやがて食料になる動物にしろ生態系を維持するためには森林が豊である地域が望ましい。自然系のシステムの中核に添うように生活することである。
縄文時代日本の自然形態はブナやナラ類の落葉広葉樹の育成に適した海洋的風土が形成されていて、東日本はブナやナラ、クリ、クルミ、などの落葉広葉樹におおわれ、縄文後期にスギ林が拡大している。縄文時代の遺跡の大部分は冬は木の葉が落ちるナラ林帯の自然に多いといわれている。。
奥多摩はクリ、ナラ、モミ、イロハカエデ、ヒノキ、ツガ、ヨグソミネバリ、トチノキ、ヤマグルマ、フサザクラ、アワフキ、ヤマザクラ、アサダ、ヒトツバ、アカメカシワ、クワ、ハンノキ、ミネバリ、ミズナラ、スギ、リュウブ、などの森林で、奥多摩の94%がそれらの森林で覆われている。
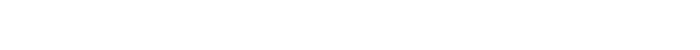
 HOME
HOME 奥多摩方面登山情報案内
奥多摩方面登山情報案内 奥多摩のすそ野は海だった
奥多摩のすそ野は海だった