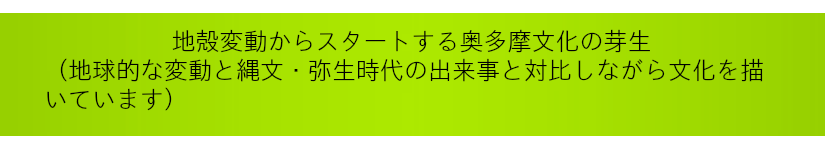![]()
2014.8.30

奥多摩・青梅の縄文時代
JR青梅線の終点が奥多摩駅である。その奥多摩駅から立川に向けての駅名は、白丸駅、鳩ノ巣駅、古里駅、川井駅、御岳駅、沢井駅、軍畑駅、二俣尾駅、石神前駅、日向和田駅、宮ノ平駅、青梅駅、東青梅駅、河辺駅、小作駅、羽村駅、福生駅、牛浜駅、拝島駅、昭島駅、中神駅、東中神駅、西立川駅、立川駅となる。奥多摩湖から奥多摩駅を含め川井駅と御嶽駅の中間あたりまでが西多摩郡奥多摩町。御嶽駅から河辺駅と小作駅の中間あたりまでが青梅市となる。青梅市内も奥多摩町同様に森林に恵まれていて、縄文人の絶好の住処となっていたと思われる。奥多摩の縄文時代の形跡だけでなく、JR青梅線沿いのわかっている代表的な縄文遺跡を挙げると。
奥多摩駅、奥多摩御前山の標高1000mからの黒曜石の石鏃。
梅沢下野原石器や縄文土器、隆起把手深鉢。
白丸駅は、白丸西の平遺跡の打製石斧、人面付深鉢。
二俣尾駅は、しない沢の敷石住居跡、桜っ原の石皿。
宮ノ平駅は、宮ノ平駅下の敷石住居跡。
青梅駅は、駒木野と小曾木の岩蔵、第三小学校、成木の小中尾などの住居跡。
森下の石棒。
駒木野の土錘。
東青梅駅は、勝沼神社裏手の井草式土器の土器片(9千年前のもの)。
河辺駅は、友田方砂の住居跡。
など、そのほかに青梅市内各所から石鏃が発見されている。
縄文土器の新たな発掘は縄文時代の定説を新たに書き直す。1988年に長野県佐久市下茂内遺跡から紀元前1万4250年前の土器の破片が発掘され、1997年に青森県蟹田町で縄文草創期の大平山本Ⅰ遺跡でみつかった土器片が、紀元前1万4500年前のものであるという。このような新たな発掘があるたびに縄文時代の定説は3000でも4000年でも伸びるという。縄文土器は世界で一番古く、日本以外で一番古い土器は西アジアの土器で紀元前6000年のもので、貯蔵用途として使用されていたと推測されている。縄文土器は文様・質量ともに優れていて、土器の底に火熱の後が示すように早くから煮炊き用に利用されていた例は存在しないといわれている。
未来は現代人が記録してゆけば後世に伝えることができる。2千年~1万年を超える大昔など記録で知るすでは殆んどない。土器や住居跡などを基にあくまでも推測である。日本はルーツを探すために、大陸で発生した文化と、3万年前以上の原人クロマニヨン人やネアンデルタール人との系譜上を探るための努力をしいる、はてしない永遠のテーマーである。
大陸から日本のルーツを結びつけるから日本のルーツがわからないのだ、日本から大陸にルーツを結び付けてゆけば、日本の古代の文明が高度文明で文化は日本から世界に広まったという可能性を示す超古代文献「竹内文献」があるという。考古学者が最大の努力をはらい、大陸との流れをひとつひとつ探すのとまったく逆説である。このことは酒井勝軍が研究したことで、武内宿彌という神功皇后 と応神天皇に深いかかわりを持つ人物からの「竹内文献」であるという。これもまた最高に興味をくすぐる内容になっている。どこかで酒井勝軍の超古代の研究内容を紹介したい。何故かと言うと、神功皇后 ・応神天皇・武内宿彌の三人の山車人形が青梅のお祭のときに登場するからである。
日本に人間が渡って来て、住み着いたのが70~80万年前という説がある。二本足で歩けるようになるまで、具体的にどのように進化して、どれぐらいの果てしない年月が掛かったかは永遠に解らない。縄文時代の上限は土器の発見とともに覆され、今は紀元前1万4500年前までをみている。土器とは別に人間の手が加わった物で一番古いといわれている物は、明石市の近くで見つかった木の板が5~7万年前のものと推測されている。旧石器時代にユーラシア大陸は日本ともアメリカ大陸とも陸続きでつながっていて、人間が自由に通行できた可能性があるという。これは、酒井勝軍も研究の中で日本とまったく同じような土器や古代文字がアメリカ・インディアンの遺跡あとから発見されたりしていることに興味を持っている。
また、フランスの人類学者クロード・レビィ=ストロース氏は日本神話と同じような物語がアメリカ・インディアンやインドネシアを含め世界のほかの地域にも見出され、日本だけにしかない話はほとんどなく、世界のあちらこちらに似たような話があり、どこの神話よりも日本の神話ほど話を構成する要素がしっかりくみ上げられている物はほかにないと述べている。
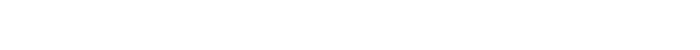
 HOME
HOME 奥多摩方面登山情報案内
奥多摩方面登山情報案内 奥多摩のすそ野は海だった
奥多摩のすそ野は海だった