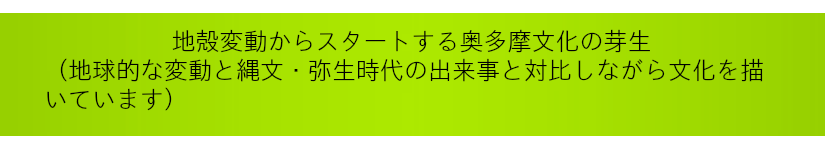![]()
中生代から描く奥多摩・青梅の文化

西多摩郡奥多摩町と青梅市の歴史
奥多摩については、武蔵野郷土史刊行会や青梅市教育委員会などの歴史物がある。青梅歴史物語と多摩市町村の歴史は、縄文時代の石器と土器や住居跡の発掘場所などの説明から始まる。そして、弥生時代、大和朝廷の歴史をくぐり江戸幕府から現代にいたるまでの歴史を、その時代々の豪族による土地の支配と、豪族が土地の支配だけでなく奥多摩・青梅の文化財を粗末せずに大切に重んずる精神の持ち主であったことなどを文化財をとおして人物像を説明している。その内容を読んでいくと、青梅市の青梅マラソンの出発地点である河辺駅から塩船観音寺間の地名などは特に古い時代の豪族が支配していた名残の地名がたくさん残っていて面白い。郷土の歴史ものを飽きさせない感じで、同じように縄文時代から現代にいたるまでをえがいている、武蔵野むかしむかし(朝日新聞社 編・川出文庫)は文の表現と挿絵が古代のようすをアニメーションのようにイメージを作って飽きさせない内容である、お勧めしたい。冒頭の一部は次のように始まる。━海底に沈んでいた日本の国土が、地殻変動でポッカリその姿を海面に現す二億年前からはじまる。奥多摩の誕生だ━ 一気に終いまで読んでしまう歴史物である。
奥多摩と青梅市成木、それに秩父山地は、石灰岩の地層が昔から存在し、現在も採掘されている。その高さは標高1000メートルを超える所もある。それは、むかしむかし、はてしない大昔、武蔵野の杣保(そまほ)または三田谷と呼ばれていた奥多摩の尾根づたいと、秩父の尾根づたいが確実に海の中にあったことを示している。
縄文時代からの裕福な自然の奥多摩は日本で最初に海面にポッポッ姿を表した所だというイメージと、はてしない大昔は海の中だったという事実をとぜひ知ってもらいながら、東京駅から青梅特快一本で来れる大自然を散歩していただきたい。
5百万年前奥多摩はまだ海の中だった
地質学によると、地球は地球自体が持っている不気味ではかり知れない巨大なパワーと、これまた、はかり知れない何億年という年月のなかで、何度も地殻変動を起し、海底にあった地層を海面上に押し上げたり、大陸を移動させたりしているという。
今から五億年前の古生代、陸地では旧大陸でユーラシア大陸などが地殻変動で姿を現していて、陸地はシダ類が生い茂る沼地で、海中はバクテリアやクラゲなどの生命がすでにあり、魚類が発生し新化し始めていたといわれている。
やがてその泥んこの沼地は、やはり、はかり知れない年月をへて、現在の石炭層となるジャングルがはてしなく生い茂るようになっていて、トカゲのような両生類が這いまわり、お化け級のトンボが空中を飛んでいたとされている。古生代は3億年にわたり、その歴史のいとなみの中で、魚や爬虫類の原型となる生物がすでに地球上で生息していた。
中生代は、科学史博物館の資料によると、約2億4千5百万年前から6500万年前までのことで、三畳紀・ジュラ記・白亜紀の三つに区分されている。温暖な気候でおだやかな変動がつづいた時代である。植物では、シダ植物やイチョウ、ソテツなどの裸子植物が栄え、後半には被子植物が隆盛となり、地上の景観を一新した。動物ではハ虫類が栄え、海・陸・空で生態系の頂点に立った。陸上では恐竜が三畳紀に台頭し、ジュラ紀で大型種が進化し、白亜紀にかけて多様化していった。空には翼竜が進出し、ジュラ紀には小型のランフォリンス類が栄え、白亜紀には飛行能力の向上した大型のプティロダクティルス類が出現した。海生のハ虫類では、首長竜、モササウルス類、魚竜が繁栄した。と、説明されている。
武蔵野むかしむかしは、武蔵野が好きな人には好みの文章となっていて、奥多摩誕生を次のように表現している。
2億年まえの古生代の終わりから中生代にかけてのできごとだ、海の底の"日本列島"が初めて経験するこの地殻変動は、ある学説によると大陸が西から東へ大移動したためだと言う。恐るべき巨大なエネルギーは、この移動の際、海の地層をちょうどシワのように上え押し上げた。貝類、サンゴ虫、紡錘虫、バクテリアその他の生物が付着する。最初の日本国土が、海面にその姿をぽっかり現したのはそのときだ。人間にたとえるなら "赤ちゃん誕生" 点々とみせた島の中に、わが武蔵野の一角があった。奥多摩の誕生である。
奥多摩を含めた秩父山地・日本アルプス・足尾・阿武隈など日本の一部誕生から、中生代の幕が上がる。
大正12年、アメリカのアンドリュウス探検隊の一行が、ゴビ砂漠で7千5百万年の間砂漠の中に埋まっていた。恐竜の卵を発見、ビッグニュースとして当時、世界中の話題となった。
海面に姿を見せた日本の島々は、そのころ少しずつ盛り上がりを見せていた。当時の日本の島々にはシダやイチョウ、ソテツなどが大森林を作っていたから、誕生したばかりの幼年期の島々のまわりには「海恐竜いたのではないか」「いや、実際にいたのだ」と、説く学者がいる。
昭和9年、そのころ日本の領土であった南樺太・川上炭鉱から、全長2メートルくらいの恐竜の化石が発見されたことがある。これは、後に「ニポノザウルス」と命名されたが、この化石とほぼ同じ物が昭和37年、こんどは九州・高島炭鉱のタテ穴9百メートルのところから発見されて話題になった。
日本の北の果てと南の果て、こう考えると、あのグロテスクな海恐竜が、むかし武蔵野の海を珍妙な格好でスイスイ泳いでいた。創造しただけでも面白い。と、表現している。
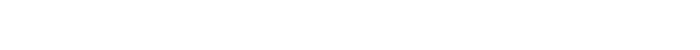
 HOME
HOME 奥多摩方面登山情報案内
奥多摩方面登山情報案内 奥多摩のすそ野は海だった
奥多摩のすそ野は海だった