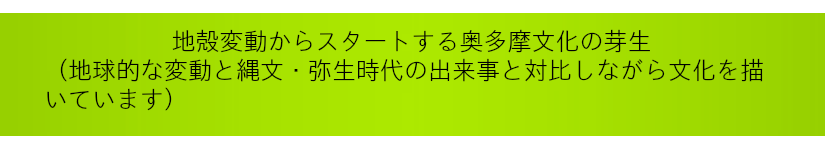![]()

奥多摩の誕生
古生代の終わりから中生代にかけて、最初の日本国土が、海面にその姿を現す。 点々とみせた島の中に、わが武蔵野の一角があった。奥多摩の誕生である。奥多摩を含めた秩父山地・日本アルプス・足尾・阿武隈など日本の一部誕生から、中生代の幕が上がる。武蔵野むかしむかしの作者のロマンのある名文句だと感服するばかりである。
幕が上がった中生代はどのような時代だったのか、自然史博物館では次のように説明している。
中生代の初めには陸上に爬虫類が繁栄し、海にはサンゴ礁やアンモナイトが繁栄しました。ジュラ紀は温暖で、恐竜が栄え、始祖鳥も出現しはじめました。この時代は、ちょうど新生代に連続する新しい地殻の動きがはじまった時代です。白亜紀には植物界に変化が現れ、それにともなって恐竜の種類も変化しました。この時代には大海進があり、火山活動も激しくなりました。中生代の後半からは、大規模な火山活動、造山運動がさかんになり、新しい時代にさかえる被子植物や鳥、哺乳類、石灰質プランクトン、硬骨魚類などの生物が出現してきました。
英仏海峡を中にはさんで、イギリスの南岸ドーバーとフランスのノルマンジー地方の海岸には数10mの高さの切り立ったまっ白い崖がつづいています。この壁の石は、チョークと呼ばれる白い石灰岩でてきています。白亜紀の白亜とは、このチョークの意味で、この白い地層をもとに設定された地質時代が白亜紀です。これは海底にたまった石灰の泥や石灰質のプランクトンの殻からなります。このチョークは英仏海峡だけでなく、世界中のいたるところに分布していて、大陸の内部にまでおよんでいます。このことから、白亜紀にはチョークのたまる浅い海が陸地の奥まで広がっていたことが考えられ、海が広がった時代と考えられています。(自然史博物館より参照)
中生代は、爬虫類、恐竜、始祖鳥などが主役の生態系。植物界の変化、恐竜の種類の変化。そして、新しい時代にさかえる被子植物や鳥、哺乳類、石灰質プランクトン、硬骨魚類などの生物の出現。しかし、やがて新世代を迎えるきっかけとなる、地殻変動や大規模な火山活動が激しくなってきます。
地球を幾度となくさま変わりさせてきた地殻変動。海底の地層が隆起する際の情景は想像を絶する凄まじさがあると思う。巨大な地震の発生、巨大な津波の発生、マグマの大噴火。それまで地球上の陸・海・空を縦横無尽に活動していた、映画やアニメのキャラクター達は生き延びるために、慌てふためきながらも必死になって逃げまわったことでしょう。しかし、自分達が生態系を保ってきた自然は凄まじいありさまのうえに、地上では食料が確保できなくなってしまう。いよいよ気が遠くなるほど長い長い古代史の歴史の中から、瞬間的といっても過言でない時を迎え、やがて滅びてゆく。
新生代に入ったころ日高造山運動と呼ばれている地殻変動があり、日本の原型に近い姿が徐々に隆起し始めてきます。しかし、ほとんどはまだ海の中でした。新生代は中生代にはなかった気候に変化が出てきます。寒冷化し寒暖の差が厳しくなり、氷期と間水期があり、これにより山すその海面が100メートル下がったり、上がったりします。その影響で日本は大陸と陸続きになったり、日本海が湖になったり日本海になったりします。
新生代は自然史博物館の説明では次のようになっている。
新生代には、恐竜にかわって哺乳類と鳥類がさかえ、植物では花をつける顕花植物もあらわれます。海では、アンモナイトや魚竜にかわって硬骨魚類が発展しました。
新生代になっても、今から1000万年前ころまでは世界全体があたたかく、それ以後の、特に200万年前ころからはじまる氷河時代になって、現在のような気候帯ができたり、高い山脈ができました。
新生代は、第四紀とよばれる氷河時代とそれ以前の第三紀とよばれる時代にわけられます。新生代(今から 6,500万年前から現在)に入ると、陸上の動物では恐竜が絶滅し、哺乳類が大発展します。哺乳類はもちろん、この時代を代表する動物ですが、それ以外にも鳥類や海では硬骨魚類の真骨魚も新生代に大発展した動物です。これらの動物は、それ以前の時代にはほとんど見られなかったもので、そのことからすると、新生代以前の時代は、私たちのすむ時代とは、相当ちがった世界と思われます。この時代、特に哺乳類は発展して、陸上だけでなく海にもすむものもあらわれます。
日本列島が、現在のような形になったのは地質時代からいえば、最近のことで。
中新世のはじめの頃(約 2,200万年前)まで、日本列島は、大陸の一部で、日本海もほとんどありませんでした。日本海に海がはいり、列島となったのはそれ以後です。日本海はそれ以後、南側が陸となり、北海道の北で海とつながった大きな湾となり、さらに湖となりました。
氷河時代に入る前に、また南側と北側が海とつながりましたが、氷河時代に何度かまた湾や湖になりました。
古第三紀の日本列島はアジア大陸の東のへりで、激しい変動があまりなかったようで、現在の日本海の広い範囲には大陸が広がっていました。
九州や北海道には内湾ができていて、そこに植物化石が堆積しました。日本の石炭のほとんどはこの時代のものです。
日本海側に大きな断層ができ、それと同時に海底火山の噴出がはじまり、だんだんと海が大陸の内側にはいりこんでいきました。この時に厚くたまった溶岩や火山灰などが緑色をしていることから、これらの地層を緑色凝灰岩(グリーンタフ)と呼ばれます。
約1000万年前、中新世の終わりのころ、日本列島の背骨にあたる中央部が隆起して海から顔を出してきます。日本海はだんだんと現在のすがたにちかくなってきます。新潟や秋田などの地域はまだ海で、砂や泥が厚くたまりました。この地層から石油が産し、ここは日本の主要な油田地帯になっています。(自然史資料館参照)
自然史資料館の説明にあるように、日本列島は中央部が隆起して海から姿を出していて、哺乳類が海に山に、恐竜に変って活動していました。このことを裏付ける歴史的発見が、奥多摩から30キロほどの昭島の多摩川で見つかりました。この発見は奥多摩の山すそはまだ海だったことを示しています。
奥多摩の山すそは海だった
約1000万年前、中新世の終わりのころ、日本列島の背骨にあたる中央部が隆起して海から顔を出してきます。日本海はだんだんと現在のすがたにちかくなってきます。新潟や秋田などの地域はまだ海で、砂や泥が厚くたまりました。この地層から石油が産し、ここは日本の主要な油田地帯になっています。(自然史資料館参照)
自然史資料館の説明にあるように、日本列島は中央部が隆起して海から姿を出していて、哺乳類が海に山に、恐竜に変って活動していました。このことを裏付ける歴史的発見が、奥多摩から30キロほどの昭島の多摩川で見つかりました。この発見は奥多摩の山すそはまだ海だったことを示しています。
昭和36年8月、多摩川に息子を連れて川遊びと化石の採集にやってきた、昭島市立多摩川小学校の田島政人教授はクジラの化石を見つけました。この内容については昭島市の商工会議所ホームページで詳しく確認できます。
(http://www.akishima.or.jp/kujira/yurai/yurai01.html)
アキシマクジラのプロローグは次のようになっています。
今から150万年前の東京湾は奥多摩の山すそから埼玉県の小鹿野、皆野、長瀞、寄居付近まで食い込んでいました。
ある日、太平洋にクジラの群れが現われ、好物の小魚を追って悠然と泳いでいました。 その中の一頭がなかまとはぐれ湾内深くと入り込んでしまいました。
そこに現れたのが太古から『海のギャング』ホオジロザメ達でした。
気がついたクジラは沖合いに去った仲間のところに一目散の帰ろうとしたが、そこは『海のギャング』ねらった獲物を逃がすわけがなく、クジラはただ、奥多摩の海岸めがけて逃げることしか出来なかった。やがて、浅瀬となり波打ちぎわとなりとうとう勝負がついた。
ホオジロザメ達はクジラめがけて飛びかかり、その鋭い歯を左の第一肋骨へ食い込ませた。肉を裂き、食いちぎりその歯の1本はそのまま肋骨に残るほどのすさまじさでした。次から次ぎとホオジロザメ達の攻撃は鋭く、激しかった。このクジラが息を引き取るまでものの数十分とはかからなかった。
やがて、クジラの残骸は少しずつ、砂に埋もれ、山から流されてきた土砂に、しだいに埋まっていきました。気の遠くなるような長い眠りにつきました。(昭島市商工会議所ホームページ、アキシマグジラ、プロローグ参照)
私たちは現在の武蔵野しか知らない。奥多摩は東京都から一番身近なハイキングコースであり、多摩川の源流でたいへん美しいところである。多摩川沿いは下流まで堤防沿いに遊歩道がある。散歩したり、ジョギングしたり、また、釣りの好きな人はマスやヤマメやニジマスを釣るために多摩川に糸をたらす。大昔昭島あたりで糸をたらしたらマスやニジマスでなく、キッとクジラやホオジロザメがつれたかもしれない。キャッチ・アンド・リリースは釣り人のマナーなんて悠長なことは言ってられない、慌てふためいて逃げたに違いない。
昔のことなど記録でしか知ることが出来ないし、誰も本当かどうかわからない、推測でしかない。しかし、アキシマクジラの化石が多摩川で発見されたことは事実である。化石を発見したり、それを学術的に結論を出してくれる人達に敬意を表したい。私たちは地球のスケールのでかさとか自然環境の変化を知ることができるし、また、それを伝えることができたことに感謝したいと思います。
アキシマクジラはホオジロザメの餌食になり、海岸の砂に埋もれてから五百万年経って、昭島の多摩川で化石となって発見されました。アキシマクジラが奥多摩の山すそを泳いでいたころ、大地は人類が生息できる環境が整っていました。
ギュンツ氷期に、蒸発した水分が雨となり海に帰らないで、氷床として大地に氷河をつくりました。そうなると、海面が100メートル下がったといわれています。そのおかげで日本列島は北海道が樺太と、九州が大陸と陸続きになりました。大陸にすんでいた哺乳類が日本に渡ってきる時期がきました。動物と一緒に祖先らしき毛むくじゃらの人類が登場したのは80万年前のことだといわれています。
人間の起源はなぞに包まれていて、現在アジア説と南アフリカ説とがあり、学名「オーストラロピテクス」という、立って歩く動物の中では一番古い骨が発見された南アフリカ説が有力だとされています。北京原人、ジャワ原人を含めサルに近い原人や旧人は道具を使っていた形跡はあるが、それが人間の先祖なのか、人間とどんなつながりがあるか、それはまだわかっていないと言われています。
日本に大陸から人間が渡ってきたとしたら、最初に住み着いたのはどこだろうか。日本が大陸と陸続きになったときに、動物と渡ってきたのだから、東洋像やナウマン像の化石がたくさん見つかっている、兵庫県明石市あたりだという説がある。直良博士が昭和6年に、明石市の海岸に近い断層から古い人骨を発見している。「奈良説」の基となる発見だった。
さらに、28年ほど経った昭和34年、こんどは静岡県三ヶ日長で、アオモリ像のキバ、オオツノシカ、オオカミの骨などと一緒に、男二人と女一人分の骨が見つかった。
奈良で見つかった「明石原人」と静岡県三ヶ日町で発見された「三ヶ日人」、これによって数十年前の昔、日本に人間がすんでいた事実がつきとめられた。
武蔵野むかしむかしは三ヶ日人について、次のように表現している。
三ヶ日人の"遺骨"が不自然に散らばっているのを見た鈴木教授は、ふと「人が食って捨てたのじゃないか」と、疑惑の目を向けたという。いまから七、八千年前の縄文時代でも、明らかに人を食う風習があったと指摘する学者がいる。骨の間接を切りはなし、日にあぶった形跡すら残っている。土器を発明したほどの"文化人"までこんなありさまだから、まして人に進化した直後の三ヶ日人が人の骨を食ったとしても決して不思議ではない。だとすれば三ヶ日人は、物的証拠を残した「日本列島バラバラ殺人事件第一号」の"犯人"かも知れない。(武蔵野むかしむかしヨリ)
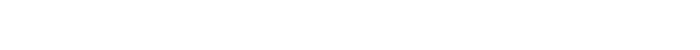
 HOME
HOME 奥多摩方面登山情報案内
奥多摩方面登山情報案内 奥多摩のすそ野は海だった
奥多摩のすそ野は海だった