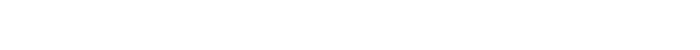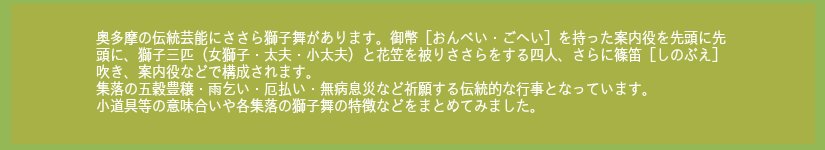|
 山祇神社獅子舞 山祇神社獅子舞
小留浦の獅子舞は、集落の鎮守、山祇神社の祭礼に奉納するもので、例祭はもとは8月29日に行われていましたが、今は8月の第4日曜日に行っています。
当日はまず山祇神社へ参詣して、「宮参り」の舞を奉納します。これは「七堂」とも呼び、集落内の秋葉神社、鹿島神社などへの奉納舞を併せて行うもので、以後は慈眼寺の庭を祭り場として舞い納めます。
獅子舞の秘典とされる「日本獅子舞の来由」という古文書は、この小留浦の村木氏から小河内の原、桧原村の沢又(藤原)、相模原の下久沢、その他各地へ伝授されたもので、ここの獅子舞はこの地方の元祖ともみられます。(奥多摩観光協会より)
編集中 |